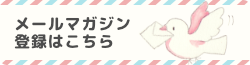- 藤原への講演依頼
- その他のお問い合わせ
| info@childhoodlabo.link childhoodlabo@gmail.com |
|
| 電話・FAX | 042-405-4181 |
| 住所 | 東京都府中市東芝町1-64-640 |
- 保育所等訪問支援に関するお問い合わせ
| 電話 | 070-2835-2708 藤原まで |
|---|
- ホーム
- ブログ
ブログ
インタビューが掲載されました。これからの幼児教育
2016/07/29背中はどこ?
2016/07/25(自分の背中はどこ?)
着替えに時間がかかる、リュックを背負っているのにそのことを忘れて人にぶつける、人の足を踏んでいるのに気付かない、後頭部の髪の毛をうまくとけない。
見えない部分はないものと捉えるイマジネーションの特性と、内的な感覚・・固有覚(筋肉や関節に入る感覚)が鈍感だという特性、原因はそこにあります。こうなると背中というのはどこにあるのか、自然にわかりにくい(感じにくい)ということになります。
この様に自分の体のイメージがもちにくい場合は、「見せる」ことと「感じる」ことを支援しましょう。背中はお風呂の時に鏡に映して見せます。「背中ごしごし」と言いながら背中をこすってあげましょう。リュックについても背負っている背中を写真に撮ってみせましょう。背中からこのくらい幅を取っているというのを理解してもらいます。後頭部も同様で三面鏡があるならそれを使って見ながらとかせるようにしましょう。イメージさせることと、感じる(感覚を入れる)ことが大切です。言葉だけで説明しても、わからないということを理解しましょう。
<お母さんとの対談:ボディーイメージがつかめない>
母:おかあさん
藤:藤原です。

母:着替えはとにかく時間がかかりました。袖にうまく腕が通せなかったり、かかとの位置を
合わせられなかったり、私の方がイライラしてついおこる・・本人はさらに体が動かなくな
る。そんな繰り返しで。
藤:私たちは袖を通すときも、かかとの位置を合わすときも、最初はその部分を見ますがその
後は見ないで身体の感覚を使って着替えをします。
見ないでできると、早いんですね。ところが、自分の体の位置や動かし方がわからないと
い ちいち見ないといけない、そしてみてもそこに体を合わせるのに時間がかかるという2
重苦 です。自然にわかりにくいので、どうしてうまくいかないのか、お母さんがなんで
怒っているの かもわからないということになります。
母:見ないとできない?なるほど、私たちは見ないでも袖を通したり、ボタンをはめたりして
いますね。それができないのですね。
藤:ボディーイメージ・・・。自分の体の実感がうまくもてないということだと思います。
体 に意識がむきにくいのです。
母:実感がないと、見ないとできないということになりますね。
藤:そうです。見て理解するしかないので、時間はかかりますし、見ても体の実感がわかない
ので、うまく動かせないということもあります。
母:いまさらですが、それは大変ですね(笑)。
藤:良かった。大変さがわかってもらえて。
ですから、まずは見せる、そして使う体の部分に意識を向けてもらい、さらに実感をもて
るように感覚を入れてあげてください。触る、握る、
押さえるなど、使う部分を実感させるように支援しましょう。
母:なるほど、見せることと実感させることですね。
藤:そこを丁寧にやることで、ボディイメージが形成されるように支援します。
母:ここでも叱らずに支援するということですね。
藤:そうです。理解が進んできましたね(笑)。子どもの脳は柔軟なので、支援すれば発達
が 進みます。
<解説:ボディイメージを育てる>
子どもは3〜4カ月のころになると、自分の手を眺めたり、前に組んだりするようになります。これは「ハンド・リガード」という行動で、自分の手を見つめることで自分に体があるということを知り、体が動く時の感覚をつかむのです。つまり「手を動かす」のを見ながら確認して、体の感覚と一致させています。徐々に、体の感覚をつかめるようになり、見ないでも体を動かせるようになっていきます。
しかし、この体の感覚、以前に解説した固有覚などの内的な感覚が育ちにくいと、見ないで体を動かすことが難しくなります。また、見えない部分を想像する力も弱いと更に動かすのは大変です。ですから、「ハンドリガード」と同じ視点で、見て自分の体を知ることと、動く時の体の感覚をつかめるように、大人が支援します。その時は手取り足取りになることもありますが、繰り返すうちに体の感覚をつかめるようになります。
実践障害児教育
2016/07/20通常学級に6%いらっしゃるADHD・アスペルガー症候群・高機能自閉症の方の特別支援教育をサポートする
月刊実践障害児教育は創刊31年となった業界のトップ雑誌です。従来は特殊学級や養護学校の先生方に主に読んで頂いておりました。最近は小中学校の通常の学級のお子さんの中に6パーセントいらっしゃるというLD,ADHD,アスペルガー症候群、高機能自閉症などの方の教育、療育をどのようにしたらよいかという教育情報にも力を入れています。文科省は『特別支援教育』と名付け、これらの軽度発達障害のお子さんと従来の特殊学級、盲ろう養護学校のお子さんを共に教育していこうとしています。そのような画期的な新時代における障害児教育、特別支援教育のために、すぐに役立つ教育実践を中心に紹介している雑誌です。
8月号が発売されましたが
「基礎から学ぶ子どもの行動と学習困難の支援」の中で
P12〜P29まで
発達障害ってなんだろうの
記事の監修をしています。
いまさら聞けない・・・というのがタイトルについていまして
もう一度基礎にかえって、確認したい方にはうってつけかと思います。
学研プラスさんのサイトは
こちらから
http://hon.gakken.jp/magazine/05261
もちろんアマゾンなどでも購入できます。
今日のつぶやき
2016/07/15園内研修:ペアレントトレーニング
2016/07/07
教員免許更新講習:E-leaning始まりました
2016/07/02発達障がいのある子の理解と支援
という6時間の講座をお送りしています。
興味のある方は
こちらからどうぞ