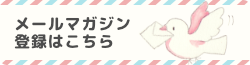- 藤原への講演依頼
- その他のお問い合わせ
| info@childhoodlabo.link childhoodlabo@gmail.com |
|
| 電話・FAX | 042-405-4181 |
| 住所 | 東京都府中市東芝町1-64-640 |
- 保育所等訪問支援に関するお問い合わせ
| 電話 | 070-2835-2708 藤原まで |
|---|
- ホーム
- ブログ
ブログ
応用講座2回目:観察のポイントとアセスメント・ご感想です
2018/05/272回目の講座が昨日ありました。
皆様に一言・・ご感想をいただいております。
次回の講座に皆さんからのお気持ちを生かしたいと思って
始めたアンケート(ミニ)ですが
あまりにも素敵なコメントが多いので
ご紹介させていただきます。
・子どもの立場に立ちきれてない・・と反省。この声掛けでつらくないかなと考えていきたいと思います。
・「叱らないで・支援を」という先生の言葉を、保護者の方に伝えてっもなかなか難しく・・・。
今回もこの言葉を聞いてまた、根気強く自分が実践していこうという勇気を頂けました。頑張ります。
・毎回こういうことなのか・・とわかる感覚と心地よさとすぐに実践できる楽しさがあります。
反面それを人に伝え、共通理解していけるような人になりたいと思いつつ、難しさがあります。
今は興味のある先生の相談を受けた時に一緒に考えていくことしかできませんが、それでも研修を生かせる場面があることに感謝
しています。
・いつも研修に参加すると、「なるほど」「そんな風に考えるのか」など、新しい発見がいっぱいです。
「やってみよう」と意気込み はあるのですが、それを支援に活かせず、どう取り入れてもらえばいいのか、
自分でうまく説明につなげることが出出ず、もどかしいのが最近の悩みです。
応用編は、学びをそれぞれの現場に伝える人材となることが大きなテーマ。そこを悩んでいる先生も多いのです。
大丈夫。まだ2回目です。残り7回でじっくり、ゆっくり、伝える人になりましょう。
また来月お会いしましょう。
ありがとうございました。

キャリアアップ研修In大阪
2018/05/25昨日、日本保育協会さん主催のキャリアアップ研修でした。
一日6時間・・しっかり研修してきました。
皆さん楽しんでいただけたかな?
この研修は今年からキャリアアップ研修になりました。
日本全国から約300名の方が集合しての研修です。
グループワーク満載の、研修ですから、300人の大迫力となります。
ペアトレのロールプレイも入っているのですが
全員で行うのはある意味圧巻です(笑)
来週は東京で同じ講座。
楽しみです。
チャイルドフッドラボ主催でも
キャリアアップ研修:障害児保育実施します。
10月29日と30日
詳細はこちらからどうぞ


委員
2018/05/23学生の頃は、○○委員という肩書は
ほぼ毎年もらうものでしたが
大人になると「委員」とは縁遠くなるものです。
でも今回2つの委員に就任するお話をいただきました。
一つは東京都の
ペアレントメンター養成・派遣事業運営委員会の委員
もう一つは
府中市障害者計画推進協議会の委員
運営も計画も未来につながるための道しるべになります。
それぞれの幸せにつながる道しるべになるように・・・。
お手伝いができること
感謝しつつ取り組みます。
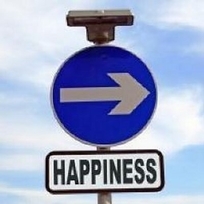
E-leaning始まりました
2018/05/22もうご存知の方も多いはず。
始まりました。
E-leaningシステムのご案内サイトはこちらから
月額約400円で
このシステム利用できます。
1年のお申し込みになります。
多くの方に知ってほしいなあ
マイページの画面はこんな感じ
コースごとに講座が整理され
受講順や
未受講・受講中・受講済みがすぐにわかる
学習の状況が一目でわかります。
皆さんからの質問受付することができて
双方向での学習もできます。

はじめまして 黒葛真理子(つづらまりこ)です。
2018/05/20みなさんこんにちは。
4月からチャイルドフッド・ラボの専属スタッフをさせていただいております、黒葛(つづら)と申します。
これから、ラボでお世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。
先日、短大の学生さんと一緒に、鶴を折りました。
スキー用の軍手をして。
固有覚を感じながら、不器用さを持つお子さんの疑似体験です。
1人がお子さん役、1人が先生役。
お子さんは苦戦しながらも、一生懸命鶴を折ります。
横から先生が励ましたり、急かしたり・・・。
ビリッと音がして、「もー!やだぁ」とうなだれたり(笑)
汗だくになりながら、なんとか鶴が完成しました。
学生の感想は、
「こんなに集中して鶴を折ったのは初めてだった。」
「折り紙が苦手な理由に初めて気づいた。」
「途中で投げ出したくなった。」
「出来上がりのイメージが出来ているのに、そこにたどり着けないイライラを感じた。」
「不器用な子ほど、みんなよりも集中力が必要なんだ・・・」
「一見頑張っていないように感じていたが、実は頑張り度合いが、他の子よりも高いことに気づいた・・・」
「こんなに頑張ったのに、簡単に出来た子と同じ評価なんて・・・」
「この苦労を知ると、こどもにどんな風に声をかけてあげたら良いのか、本気で考えた・・・」
子ども役になってみて、初めて気づいたことがあったようです。それぞれが、若くて柔らかい心で感じ、たくさんの感想が出てきました。
子どもの行動の理由が分からなかった頃、私も子どもを一生懸命励ましていました。
子どもの行動には理由があり、自分とものさしが違うこと、それを知った時、ハッと気づかされました。
目の前の子どもに、どんな声をかけるか、どんな気持ちで向き合うか、真剣に考えました。
そこから、私も学び始めました。
これから、ラボを通して、多くのお子さんや、ご家族、支援者の方と出会わせていただけることを感謝しつつ。
どうぞよろしくお願いいたします。

基礎コーズ2回目
2018/05/20今回は感覚統合理論の話がメイン。
多動と不注意な子のアセスメントと
その仮説に基づいた支援についてお伝えしました。
いつも通り遊びの紹介、グループワークもたっぷり実施。
楽しん学んでいただけたと感じています。
来月は、不器用ちゃんの理解と支援。
単発の受講も受け付けていますので
メールでご連絡ください。
受講料金は1回2500円となります。
毎回のテーマについてはこちらからご確認ください。


昨日と今日
2018/05/16昨日は午前中保育園訪問。
夜は羽村市の法人さんの研修でした。
研修内容は「ソーシャルスキルトレーニングを保育に活かす」
そう、ソーシャルスキルトレーニングは
保育の中で自然に営まれているものなのです。
「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ。」という名言がありますが
まさにこれ。
教示➡モデリング➡リハーサル➡フィードバック➡搬化(実際の場面で活用する)
です。
昨日は、保育カリキュラムのねらいを
子どもここに「めあて」として意識させるプログラムを皆さんで考えました。
「めあて」というのは、例えばお店屋さんごっこで
子ども自身が「ここを頑張りたい」と考えることです
・優しい声であいさつする
・買ってくれる人に喜んでもらえるように丁寧につくる
など。
これを子どもに提案し、選択してもらうことにより
モチベーションも上がるし、必要なスキルもより強調されて練習できます。
こちらの誉め所もピントが合うというもの。
今回の研修は3回シリーズで、実践できるソーシャルスキルトレーニングを目指します。


和光市発達支援事業所Roots
2018/05/15昨日はスーパーバイズでした。
発達支援事業所R00tsさんです。
和光市駅から徒歩5分。
便利なところになります。
でも一般家庭のような建物でとてもアットホーム








発達が少し心配という方は気軽にご相談もできます。
和光市以外の方もご利用できます。
藤原も月に1回はスーパーバイズに訪問してます。
昨日.は午後から勉強会も
20名の方が片寄せあって、学びあい。
沢山のご質問、ありがとうございました。
また是非機会を設けましょう。
勉強会の合言葉は
ただ一つ「多様性への寛容さ」
所ジョージさん
2018/05/13何でもかんでも規則どおりにやらせようとするのは機械の仕事。人間なんだからいろいろな場面で臨機応変に対応しなきゃ。
あなたなんて居ても居なくて も同じ、って言われたら、 「居てもいいんだ。ラッキー」って思っちゃうもんね。
ヒザが痛かったら、痛むヒザ で何ができるか考えれば いい。
いいとこ探しに名人、考え方次第で幸せは目の前にあるということなんですよね。
苦しい時に忘れてしまいがちなことを思い出させてくれる。
私もそんな「人」でいたいと思います。

今週は
2018/05/12今週は




4本の研修・・でした。
来週からも平均週4本の講座や研修を6月まで
1本1本大切にこなしていきます。
そのためにも体調管理が大切。
喉もケアしないと。
以前300人対象の研修の前に喉をつぶして
本当に聞き苦しい声でお話しした苦い経験が
年齢とともに声帯もそれほど強くなくなってきているような気が・・。
声をほめていただけることが多く、自分の声は好きでなかったのですが
だんだん好きになってきました。
これも皆さんのおかげです。
研修動画もきちんとE-leaningシステムの載せるために
作業中。楽しみにお待ちください。
素敵なマイページを提供できると思います。

瑞穂町発達サポーター認証講座
2018/05/08今日が1回目でした。33名のご参加ありがとうございます。
あと6回、楽しく学んでいただけるように努めます。
マッサージの効果を報告いただいた先生。
リソーススペースの使い方に苦慮されている先生。
4月になり教室を出て行ってしまうお子さんの支援に丁寧に取り組む先生。
私もお手伝いさせていただきながら
共に考え前に進んでいけたらと考えています。
来月またお会いしましょう。
お疲れ様でした。
そしてそして
後援いただいた瑞穂町・・お手伝いいただいた石畑保育園さん
感謝しております。
今後ともよろしくお願いいたします。

取材協力のお申し出ありがとうございます
2018/05/05今回学研「ほいくあっぷ」の取材をさせてくださいと
メルマガ会員の方に呼びかけたところ
10園以上のお申し出がありました。
ありがとうございます。
5月、6月の訪問先は決定しましたが
それ以降の園は、現在調整中です。
2019年度もこの連載の続投が決定したので、あと6園は訪問できる予定。
遠くは熊本(こちらは取材が難しいということになりました)
小田原(こちらは取材を検討したいので再度ご連絡いただけると助かります)
の園さんからも、コンタクトいただきました。
みなさん、もうしばらくお返事お待ちください。
「ほいくあっぷ」のご紹介動画はこちらからご覧になれます。


遊びの講座
2018/05/03楽しかった〜
ルミエール府中のレクレーションルームは
あそびを体験するには最適の会場でした
会場に入った途端、気持ちがぐっと上がりました。
皆さんが楽しく遊びを学んでいる絵が浮かんできて
始まる前からワクワクしていました。
安心して、子どもが遊べるコツや
アイデアを
そして、子どもの脳の働き方のうまくいかないところを
遊びで発達させましょう!!という講座
遠くは愛知、静岡からのご参加もいただき(1時間30分の講座のために)
総勢50名・・1時間半遊び倒しました。
(もちろん専門的なレクチャーもしてます(笑))
今日の一押しの遊びは「おちゃらかほい」
安心藤原バージョンで、ご紹介。
この遊び昔好きだったんですよね〜
次回は2時間にしてさらにバージョンアップしたいと思います。
今年度中に企画できるかな?
パラバルーンの遊びも取り入れたいので・・(バルーンのインストラクターの先生に交渉済み)
そうしたら、3時間コースにしないといけないかも
決まりましたら、お知らせしますね。


1日で学ぶペアレントトレーニングご報告
2018/05/01昨日はペアトレの一日講座
ゴールデンウイークの行楽日和のなか
1日学ぶ皆さんに感謝しながら
楽しく学んでいただくように、藤原・・・がんばりました。
50名の方のご参加・・。レクチャー、グループワーク、ロールプレイと盛りだくさん。
学研の取材の入っていましたが
いつもと変わらぬ、熱い(暑い?)内容となりました。
ご夫婦でご参加された方
早速メールで昨晩の家庭での効果をご報告してしていただきました。
その他、アンケートから感想を一部ご紹介します。

・シンプルは方法を教えていただき、すぐ実践できそうだと感じた
・藤原先生のペアトレを広めていきたいと思いました。温かい親子関係をづく理を基盤にしているのがとても良いと思いました。
・実際に子供で体験したみたい意欲がわいた。今まで悩んでいたことのヒントに大いになった。
・発達障害の子どもを持つ親としてなぜ子どもが親の言うことを聞かないのかがわかり
親として何が大事かを再確認できました。
・実際にロールプレイすることで、子どもの気持ちをこうだったのかなと理解していくヒントになりました。子ども自身の対応、今が対峙な時と感じ今後は気持ちに寄り添っていきたいです。
・子どもの行動について、どのように考えていったらいいのか、理解する糸口を見つける考え方を学べた
・母親とのつながり、母親への支援は欠かせず、そこでの子育てのエッセンスとして大切なことが沢山ちりばめられていたと思います。
・子どもたちとの信頼関係をつくることもそうですが、周りの大人の方と関係を良いものにしていくことにも役立つと思いました。
・見て見ぬ振りがどうしても難しかったが、好ましい行動の指示を出しながら自然とできるというのはすぐに実践できると思った。
・ほめて育てる=甘やかすことではないこと、ほめて育てる=子どもの気持ちを受け止めること
・ロールプレイをたくさん行い、こんな声掛けをいいとか、タイミングや目線の高さとか実感できたことが良かったです。子ども側の気持ちを経験できた子どもすごくよかったです。