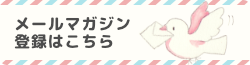発達障害を含めた多様な発達のお子さんの理解と支援をお手伝いします。
- 藤原への講演依頼
- その他のお問い合わせ
| info@childhoodlabo.link childhoodlabo@gmail.com |
|
| 電話・FAX | 042-405-4181 |
| 住所 | 東京都府中市東芝町1-64-640 |
- 保育所等訪問支援に関するお問い合わせ
| 電話 | 070-2835-2708 藤原まで |
|---|
- ホーム
- ブログ
ブログ
障害児保育
2017/01/283年前から非常勤講師で、保育士や教員を目指す生徒たちを教えています。
今日は後期の最終授業でした。50名強の生徒数ですが、初めて全員そろいました。
というのは、実習がはいったり、授業以外の大切な活動が入ったりして
なかなか全員出席は難しいのです。
授業では、知識や技術なども実践的におしえていくのですが
何より大切にしているのが、多様性への寛容さです。
元々人は多様であり、自分と違う人たちとつながりあい
支えあい、そして理解しあう努力をすること。
そのために知識や技術を学ぶのです。
環境や対する人により、子どもの価値が変わるわけもなく
だからこそ、私たちが自分のものさしで子どもをはかったり理解する怖さを
十分に理解してもらいたいと。
今からテストの採点します。

嬉しいメッセージ
2017/01/25今、療育現場の最前線で働く素敵な人からのメッセージ。
お疲れ様です!本日3日間の研修を終え、感じる事は日々勉強、また他施設を見る事の大切さを痛感しました。そして何より最近特に感じていた事は、何年も藤原先生のところへ通い実践研修や講習を受けてきた知識は本当にどこへいっても通用する、とても大きな財産だなぁと感謝しています。
いつかこの感謝の気持ちを伝えたいと思っていたのですが、こんなメールで失礼します。
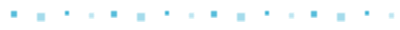
うれしいなあ。また明日からがんばります。
大切なことを教えてもらっているのは、私のほうです。
学び続ける仲間に感謝。

ペアレント・プログラム
2017/01/23来年度、小平市にあるNPO法人子ども未来ラボさん
http://www.mirailabo.org/
企画のペアレントプログラムをお手伝いすることになりました。
私がペアレントトレーニング6セッションを保護者の方たちと行い
そのペアトレを支援者の方たちに実際に見ていただき
方法を学んでいただくというものです。
つまり、保護者の方はペアトレを体験し
支援者の方はその内容を研修するという
システムです。
このプログラムの実施マニュアルも作成し
支援者の方は、次は自分たちでペアレントトレーニングを実施できるようにします。
こうして、必要なご家族たちにペアトレが広がっていくことを目ざします。
ここで大切なのは、ペアトレは万能ではないので
他の支援方法論も知っておくこと
そして何より大切なのはお子さんの発達特性の理解を
できるだけ進めたうえで、実施すること。
私のペアトレは6回のうち2回は、お子さんの発達特性の理解と支援に時間を割きます。
いずれにしても、ご家族も支援者も学びあえる企画になります。
この企画に先立って、6月17日土曜日午前中に
小平市内で講演会を行うことになりました。
詳細はこれからですが、子どもの見方を変えることで
子どもの才能を伸ばすことができますよ!!
ということを伝えたいと思います。
詳細が決まったら子のHPでご報告しますね。
子ども未来ラボさんのHPより
素敵な画像をお借りしてきました。

新しいご縁
2017/01/20来年度から、埼玉県の発達障害総合支援センターのお手伝いをさせていただくことになりました。
今日はその打ち合わせに行ってきました。
地域の保育士さんをはじめ、早期からの発達支援をする方たち.
保護者の方たちの人材育成のお手伝いです。研修もやります。
埼玉県はオリジナルの研修テキストも作成していて
これがコンパクトながら、よくできています。
私の著書と融合させる形で
研修を組んでいく予定です。
600人以上の方たちと、出会えるようでワクワクしてしまいます。
このご縁を結んでいただいたのは、私の敬愛するお医者様です。
ありがとうございました。
スタッフの方々も、いい方ばかりで、本当に私は出会い運はもっているんだなあと
感謝の気持ちでいっぱいになります。
できたばかりの、施設はピカピカでした。

お礼の手紙
2017/01/19昨年の12月、群馬県館林市の保育士さんの講演会にお招きいただきました。
館林保育研究会さんの主催でした。
70名ほどのご参加がありまして、疑似体験、演習、遊びなど盛りだくさんに
学んでいただきました。
帰りには素敵なお花もいただきまして
本当に楽しい時間を過ごせました。
今日、主催いただいた会の園長先生から
お礼の手紙をいただきました。
皆さんからの感想もいくつか記載していただきまして
「わかりやすいお話でズバリ私たち保育士が知りたいことや困っていることへのアドバイスをもらえて
有意義な時間でした」
「発達の木になる子供について、どうしたらよいのか悩んできた時に、藤原先生の講演会があり、とても勉強に
なることばかりでした。その子にあったかかわりを丁寧にゆったりとして気持ちで保育をしていこうと思いました」
「実践できる脳の働きを促したり、多動性を知る指標となるあそびを楽しむことができ、園でも実践していきます」
「気になる子のコミュニケーションにも要求や注目などそれぞれ違う意味があるということを実感できました」
「子どもたち同様に保護者の気持ちも理解し、受け止めることを忘れずに支援していきたいと思います」
最前線の現場で、真摯に子ども達に向き合い、学ぶ皆さんを尊敬し応援しています。
またお会いできる日が来ますように。
滝先生、お手紙ありがとうございました。

毎日・・・。
2017/01/18月曜日:保育園の訪問、火曜日:発達支援事業のスーパーバイズ、水曜日:保育コーディネーター研修
明日木曜日:保育士・学童クラブ指導員さんへの研修 明後日金曜日:発達支援センタースーパーバイズと
盛りだくさんの週です。





相談すること
2017/01/15今日は強い寒波がきているとのこと。
でも東京はきれいに晴れています。
我が家の長男は今日から沖縄修学旅行。
笑顔で出発しました。
さて、金曜日に、センターで実施して連続講座はご家族の支援についてお話ししました。
明日、月曜日は来年の学研「ほいくあっぷ」の取材で
ある保育園にお邪魔して、スーパーバイズしていきます。
その時の中心的テーマが、子どもへの声のかけ方・話し方について。
この連続講座も明日のスーパーバイズも
大切なのでは、相談するということです。
問題を抱えているご家族、お子さんに
どんな声をかけ、話をしながら問題を解決するのか?
つまり相談する・できるように、支援者が声掛けや話の持ち方で導くのです。
いろいろな、専門理論がありますが
「問題解決コラボレーション」というモデルが参考になります。
私も
この方法を学んで、かなり意識して子どもとの話し合いや
ご家族の面接に使っています。
3つのステップがあるのですが
最初の共感ステップがやはり何より大事です。
自分の視点と違う相手の共感するのは
やはり、トレーニングが必要だと思います。
元々の資質として、多様な人に共感しやすい方もいれば
そうでない方も。
ここも実や多様です。
また、共感の感性をあげるためには
自分の傾向をしっかり把握しておくことと
多様な発達の知識を持つことが必須です。
この内容は、来年度の連続講座
応用編夜間と、コーディネーターコースで盛り込みたいと思っています。
そのほか、今まで研修ではなかなかお話しできなかった
専門理論についても、来年度の連続講座では
盛り込んでいきたいと思います。
「問題解決コラボレーション」については、
こちらの本で学べます。

発達教育の「巻頭言」
2017/01/13
公益社団法人「発達協会」さん。
発達障害や知的障害のある子・人への医療・療育と研修・出版などをされています。
月刊誌を発行されていて、ご存知の方も多いと思います。
2月号の「巻頭言」を藤原が書かせていただくことになりました。
テーマはご家族の支援です。
ご家族を支えるためには
お子さんの困っている「その子らしさ」を通訳して
お子さんの良き理解者になっていただくこと。
支援者の役割がそこが大切ということを、書きました。
明日から、強い寒波が来るようです。
温かい家の中で読書する1日になりそうです。
事例検討:インシデントプロセス法
2017/01/11今日は、保育士さん対象の研修でした。
回を重ね8回目の研修。今まで学んできた知識を生かして
事例検討をしました。
担当のお子さんが持つ問題に対してどう支援するかを
情報を集め、分析し、支援を見出していきます。
その方法としてインシデントプロセス法という
方法を用いました。
この方法は、参加者が当事者と同じ立ち位置で
とにかく肯定的にできる支援のアイデアを出し合うというもの。
どのアイデアにも「Good!」のリアクションを返すのが約束事なのです。
ですから、安心して意見を出し合える
だって、だれも否定する人がいないから。
そのアイデアが、有効か、できるかどうかより
こうしてみたらと活発に言い合えることを大切にしている方法なのです。
最終的には出たアイデアの中から、事例提供者が使えるもの
やってみたい支援を選択すればいいのですから。
今日はこの話し合いの結果を
グループごと模造紙に記載して発表しあいました。
デスカッションしている間は、まさに白熱教室という感じ。
今日の成果の一部をを画像で載せておきますね。
楽しい研修でした。
皆様お疲れ様でした。






身の丈にあう
2017/01/11所ジョージさんが、某ビールのコマーシャルでいいました。
「自分のことをすごい人間だと思うから落ち込むの。身の丈になっても、光ることたくさんあるからね」
といいました。
これって本当にそうだと思います。
ほめて育てることは大切だけど
発達障害をもつ子どもは、自分をモニタリングするのが苦手で
「あなたはすごい」とほめられ続けて「自分をすごい人」と思ってしまうと
イメージ通りにできなかったときの落ち込みがとても激しい。
あなたはかけがえのない人・・大切な人・・というほめ方
行動を具体的にほめることなどを意識することが、支援者には必要だと思います。
そうでないと、「すごい自分・・・でも、思った通りできない⇒パニック・怒り・不安」
となる、
身の丈に合うことを、選択できるようにすること
そのためには、自分の身の丈を知ることだと思います。
できないことがあっても、そういう自分をかけがえのないものとして、感じられる。
それは人と比較しないこと・・周囲の大人がそこに真摯に取り組むことだと思います。
身の丈にあうことを、真摯に取り組むことの大切さをどれだけ子どもたちに伝えらえるか?
あるお母さんは、「子どもの身の丈にあうことを、大人が選択することが難しい・・目標をその子に合わせて下げることが」
といい
「でもそのことが、本当に大切だと藤原さんのお話を聞いて、思いました」と、微笑んでいらっしゃいました。
これからも、様々な葛藤がお母さんの中ではあることは予測できますが
それでも、今回感じていただいたことは、心の中で響き続けると思います。
私の方が励まされました。ありがとうございました。

今年のチャレンジ目標
2017/01/08年が明けて早一週間。
今年は新しいこのラボの活動を中心にお仕事をしていくわけで
それだけでかなりのチャレンジになるのですが
もういくつか目標を掲げていきたいと思っています。
最優先は、アロマについて学ぶこと
できれば検定試験も受けて、資格も取りたいと思っています。
多様な発達の子供たちが不安を強くしたり、体調をくずすことに対して予防的にかかわりたいと
思っていまして、そのためにはこのアロマが有効だと考えてきました。
実際、センターの療育でもアロマのプログラムを実施しています(専門家の先生からレクチャーを受けたりしながら)
すると、子どもに変化がみられるのです。
また、香りが一つのお守りのような役目も果たし
不安、イライラなどネガティブな気持の在り方を
調整してくれるのです(この香りがあれば大丈夫という感覚を持てることも多い)
香りはダイレクトに視床下部に届くといわれています。
視床下部は自律神経の働きを調整しています。
また、体温調節や、内臓、内分泌系にも影響します。
体や心の調子を整えるのはもちろん、生きることに必然な
働きを支えているのです。
周囲の環境に左右されず、体内環境を一定に保つ・・安定した状態にすることを恒常性といいますが
視床下部の機能が整うことでこの恒常性が保たれるのです。
周囲の環境の変化で、体調を調子を悪くする子どもたちのために
学んで、その知識を立てたい・・日常生活の中で
無理なく取り入れる方法を考えたいと思っています。
もちろん
研修の中にも、取り入れ、皆さんと学びをシェアしたいですし
保育、教育、育児のなかにも取り入れていただければと考えています。
ちなみに私のお気に入りの香りは
ベルガモットです。

スーパーバイズと保育環境
2017/01/06今日は、都内の発達支援事業の療育に対するスーパーバイズでした。
お子さんの注目行動に対するかかわり方
ご家族の方への伝え方
個別学習の設定
集団プログラムの考え方
食事の際の対応
そのほか、いろいろな内容を伝えたりディスカッションしたり
1日の様子を見たうえでのことなので
かなり具体的に、明日からできることを提供できました。
研修も1時間ほど実施。
インリアルアプローチについて。
そして、不安の強い子がいかに能動的に遊ばせるかについてなど。
いやいや振り返ると本当に盛りだくさんの1日でした。
4月からは、保育園、幼稚園、療育施設など現場に出向いての
スーパーバイズが増えます。
楽しみ。
今日ご紹介する写真は、私の研修を受講して
保育現場で、現場に合わせてカスタマイズして支援を実施している園から提供いただきました。
参考になるものがたくさんなので、ぜひご覧ください。

遊びのコーナー分け

ままごとコーナー 入口子供の目線にインデックス

絵本コーナーには座り心地の良いビーズクッションなど

絵本はしまいやすいように絵本のテープと本棚のテープの色が一致
思わず定位置に片づけたくなる工夫

お絵かきとカード遊びコーナー

ふわふわ言葉を言うと、クラスでかわいい瓶に貯金
 瓶がいっぱいになると、かわいい木にみがなります。
瓶がいっぱいになると、かわいい木にみがなります。その名もふわふわの木・・本当にフワフワしている、幸せな気分です。

ブログの効果?たくさんのアクセスありがとうございます。
プラスその行動にピンときたら不安対策!!
2017/01/05
ブログを毎日更新するようになって早5日。
HPのアクセス数が伸びています。
たくさんの方にラボを知っていただくのはうれしいこと。
ありがとうございます。
連続講座初級者コースも50名定員のところ
30名ご応募いただいております。
4月から始まるのですが、参加を予定されている方がいらっしゃいましたら
早めのお申し込みが良いかと思われます。
さて、今日の話題は
今日は、小学生のグループ新年最初の回。
私はこのグループに入っていないスタッフでしたが
今日は見学参加しておりました。
諸事情によりお部屋入室できない子がおりました。
原因はいろいろ考えられるのですが。
最後の最後に入室して、なんとか過ごすことができました。
その子がメンバーに「ねえねえ、そこの緑の子」(来ている洋服が緑色でした)
と呼びかけているのにピンときました。
名前と顔を覚えられていないのです。
グループ5回目ですが、誰一人わからない状態。
それは不安で仕方ないはず。
私:「ねえ、メンバーの写真をとって、メンバー表を作ろうと思うんだけどどう?」
彼:「もう帰るまで2分しかないから、写真撮れないでしょ」
(本心:作ってほしいよ。安心するから)
私:「大丈夫、とるよ。とってメンバー表つくるよ。知ってる子は○○くんだけだもんね」
(以前一緒のグループで仲良しだった子なので、唯一顔と名前がわかる子が一人いたので)
彼「全員は無理でしょ、だってかえって子もいるし」
(本心:作るのできないじゃん。不安だよ)
私:「来週、かえって子もとって、絶対作るよ。大丈夫」
彼:うなづく
ああ、これも原因の一つだ!!
そうなのです。顔と名前を覚えられないというの
本当に不安なこと。誰かわからない子たちと仲良くなんてふるまえないわけで。
5回も合えば顔見知り・・にはならないのです。
もちろんこれだけではないと思うのですが
その子の不安の原因がわかることで、本人も支援者も安心するのです。
だって対策が見えてくるから。
その行動にピンときたら、不安対策。
安心が一番大事なのです。

嬉しいお知らせと才能
2017/01/04今日から仕事始め。
懐かしい人が訪ねてきてくれました。
小学校で描いた絵が、賞をもらったとのこと。
その素敵な絵はカレンダーにもなりました。
素晴らしい才能を秘めていたのです。彼は。
すっかり背も伸びて、少年になっていましたが
ボールプールに入っている笑顔は昔のままでした。
最後は照れて、あいさつもうまくできなかったね。
でも、そんなお年頃です。
その姿にも成長を感じてしまいました。
子どもの才能を見出すのは、大人の大切な役割ですね。
私の才能は??
ポジティブシンキングにつきるでしょう。
後、緊張しないこと(笑)
仕事をするうえでこの才能は欠かせません。
明日から仕事始め
2017/01/03お正月3が日も今日で終わり
明日から仕事始めの方も多いのではないでしょうか?
私も、仕事始めです。
今日は、たっぷりマッサージをしてもらい
肩こりやら、背中の痛みを解消してきました。
フットマッサージも受けてきたのですが、足裏のマッサージの痛かったこと
どこのツボなのか?やはり体のあちこちにガタが来ているのか?
まあ、今は楽になったのでよしとしよう。
固有感覚にもたっぷり心地よい?刺激が入力され
明日からまた頑張れそうです(笑)
この子にも癒されました。このお正月ずっと一緒でした。

さあ、今年も頑張って働きましょう!!
障害児保育ワークブック
2017/01/02私の敬愛する星山麻木先生
明星大学の通信制大学院で私は星山ゼミに入りました。
そこからのご縁で、先生の教えや活動の刺激を受けながら
今も学会で協働させていただいています。
先生からお声掛けいただいて、本を執筆させていただいたのが2012年。
いま、明星大学の「障害児保育」の授業でもその本を使っています。
「障害児保育ワークブック」という教科書。
私は2章執筆させていただきました。
この春、改訂されます。今日はその本の執筆部分の
修正箇所を確認していました。
その後も学研さんとご縁をいただいて
本を出版させていただきました。
このご縁は本当にありがたいことで、本を出版したからこそ
私の考えていることがより多くの人に知ってもらえる機会になりましたし
そのことにより、多くの方たちとの出会いやご縁をいただきました。
書いているときは大変ですが・・・、出来上がった時の達成感は大きい。
素敵な編集者や、ライターさんに助けられ
生み出された本。
これからも大切にしていきたいと思います。
あけましておめでとうございます。
2017/01/01新年にふさわしい快晴(東京)!
今年は、新しい環境に身を置きます。
不安よりもワクワクしている自分が心地よい。
新しい出会いもたくさん待っているでしょう。
今年は自分の新奇親和性を十分生かして
歩んでいきたいと思います。
皆様にとっても、素敵な1年になりますように。

チャイルドフッドラボ
藤原里美