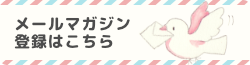- 藤原への講演依頼
- その他のお問い合わせ
| info@childhoodlabo.link childhoodlabo@gmail.com |
|
| 電話・FAX | 042-405-4181 |
| 住所 | 東京都府中市東芝町1-64-640 |
- 保育所等訪問支援に関するお問い合わせ
| 電話 | 070-2835-2708 藤原まで |
|---|
- ホーム
- ブログ
ブログ
心の育ちをサポートする5
2019/01/20「安心ボックス」でアイデアを提案する
●不安を解消する「安心ボックス」
ひとつのやり方として、「安心ボックス」をおすすめします。
多くの子どもたちが不安を感じるのは、次のようなときではな
いでしょうか。
・はじめての活動
・負けたとき
・失敗したとき
・急な変更があるとき
・強い言葉で指示されたとき など
そんなとき不安を解消し、落ち着きを取り戻すためのアイデア
の提案として「安心ボックス」を用意しておくのです。そして、子
どもたちに自分で選んでもらいます。発達障害のある子は、感覚
が鋭敏な子どもが多いですので、なんらかの刺激や動きを入れてあ
げると落ちつくことがあります。伸縮性のあるボールをギューッ
と握ったり、トランポリンを一回飛んだり、へびごまをさわったり、
オイル時計のような動きのあるものを見たり、アロマをかいだり
……。そうすることで、苦手なことでもやりようはある、乗り越えら
れる、と実感してもらうのが「安心ボックス」です。
たとえば、年長さんでゲームに負けると怒ってしまう子(既に何
度か安心ボックスを使っています)には、「安心ボックスから何を使
う?」と聞きます。
すると「今日僕はミントとオレンジスイートの香りをかぎます」と
自分から言うのです。そのアロマオイルを
ハンカチにしみこませ、怒ったときかぐことで、その子はゲーム
に負けても怒らずに済みました。
幼稚園バスに乗れないと言う子が、ミントの香りをかぐことで
乗れるようになったり、ADHD(注意欠如・多動性障害)の子が
マッサージの道具で腕をコロコロしてあげるだけで落ち着いたり。
こうしたことで子どもは落ち着きと自信を取り戻していきます。
学研教室でも、できる範囲で「安心ボックス」を用意しておか
れるといいのではないでしょうか。具体的な物でなくても、「冷た
い水を飲む」「教室をひとまわりする」といった行動をカードに書
き何枚か用意しておくのもおすすめです。「知識とイマジネーショ
ン」でアイデアの引き出しを増やしていきたいですね。
心の育ちをサポートする4
2019/01/11子どもの心に寄り添いながら共感→受容→提案する
発達障害がある子どもたちと接するとき、その子たちの心の状
態に寄り添って支援する、という姿勢がとても大切です。
私が研修に行った園で出会った、ASD(自閉症スペク
トラム障害)の男の子の例を紹介します。
ASDの子は急な変更が苦手です。その日は、外遊びのとき、
最後にゲームをするはずだったのに、時間が足りず急にや
らないことになりました。その子は大変なパニックにな
り、泣いて怒っていました。
担任の先生は、「君の気持ちはわかるけど、あきらめよう
よ」と説得していましたが、彼の気持ちはおさまりません。
そこで私は、彼に次のように話しかけました。「急にゲームがな
くなったんだって? それは泣いちゃうよね、怒っちゃうよね。
君の気持ちはよくわかる。怒るのは当然だと思うよ」。すると、そ
の子の声のトーンがすとんと落ちました。さらに私は続けました。
「問題なのは急に変わったってことだよね? 君はゲームがなくな
ることを知らなかったんだよね?」と言ったら、彼は「そうそう」
とうなずきました。「だったら、急に変えるのはやめてって先生に
お願いしたら?」と言ったら、もう泣くのをやめました。そして、
先生のところに行って「先生、最初にゲームがあるかないか教えて」
と自分の言葉で言ったのです。先生は「わかった、そうするね」
と答えました。彼はほっとした顔になって、給食を食べに行きま
した。
「そんなことぐらい?」と思われるかもしれませんが、彼にとっ
てゲームがなくなるというのは「そんなことぐらい」で済むこと
ではなかったのです。泣いて怒るほどつらいことだったのです。
それを、大好きな先生に「そんなことぐらい」と思われたら、彼
の心はさらに傷つきます。そして、その後も彼のつらさを無視し
た対応がくり返されたら、彼は「またか、また叱られるんだ、ま
た僕が悪いのか」と、どんどん自己肯定感を低めていくことにな
りかねません。
共感して、受容して、提案する。子どもの心を育てるには、ま
ずは「共感」が大切だと思います。
「こうしなさい」と押しつけるのではなく、しっかり共感して心
が開いてから、「これ、どう?」と提案する。そうすると、子ども
たちは素直に聞いてくれると思います。
次回に続く・・・
心の育ちをサポートする3
2019/01/06その子の〝ありのまま〟を受け容れ、必要な支援を
先に挙げた男の子の例のように、私たちは大きく「波長」が違う子
だとありのまま受け容れようとするのですが、難しいのは、少し「波長」
がずれている「パステルカラー」や「グレーゾーン」の子どもたち。少
しずれているだけだからと、多数派に合わせようとしがちです。
たとえば、アトピー性皮膚炎や小児喘息は、それを治療しても、そ
の子のアイデンティティは傷つきません。ところが、ADHD(注意欠如・
多動性障害)やASD(自閉症スペクトラム障害)の傾向がある子ど
もの困り感を修正しようとすることは、その子自体を傷つけることになるのです。
なぜなら、ADHDもASDも、その子の大切なアイデンティティであって、
強みでもあるからです。多数派と大きく違う「波長」を持っている子が、
集団の中で一方的に「あなたの行動はおかしい。多数派に合わせなさい」
と言われ続けるとどうなるか。自分のアイデンティティを攻撃されていると感じます。
そして、傷つき、心が委縮してしまいます。
私は、多数派と「波長」がずれている子どもたちを、「標準の発達
に近づくようトレーニングしよう」などとはまったく思っていません。た
だ、私たちの世の中は、多数派が生活しやすい環境になっていますので、
その子が生活しやすいよう、アイデアを出したり、一緒に工夫したりして
いくことは必要です。
「あなたは大切な存在。そして、あなたの多動や衝動性はあなたの
強みなのよ」というメッセージを伝えつつ、「でも、こういう場面では
困っているみたいだから、こんな工夫をしてみようか」と提案する。根
気が要りますが、こうした向き合い方、サポートのしかたが、心を育て
る上で大切だと思います。
心の育ちをサポートする2
2019/01/04気になる子どもの特性を「長所」ととらえて接する
●ADHD(注意欠如・多動性障害)の子ども
特性 衝動性が高く、多動
↓
長所 思い立ったら即行動
多動のエネルギーをうまく生かして、興味のあることに結び付けてい
くとよいでしょう。好きなことへの集中力は非常に高いです。たとえば、
虫が好きなら、すべて虫をテーマにする。漢字でも、虫の名前が出て
くる問題にしたり、算数でも虫が出てくる計算の文章題にしたりなど。
本人の好きなことを中心に置くと、取り組み方が違ってくると思います。
また、どうしても動いてしまうので、10分集中したら動くような働
きかけも効果的です。必要な感覚が満たされると落ち着き、次の10分
に向かうことができます。
コツコツやるのは苦手なので、短い時間で集中して、「できた」「でき
た」を積み重ねていくと、楽しく学習できると思います。
●ASD(自閉症スペクトラム障害)の子ども
特性 いつもと違うことが不安、こだわりが強い
↓
長所 同じことを見事に再現できる、こだわりを生かす
ASDの子どもは見通しを持っていて、それと違うことが起こるのが
とても怖いのです。「いつもと同じ」が安心します。柔軟に思考できな
いため、急な変更がとても苦手で、気持ちや行動を変化にフィットさせ
ていくことにエネルギーを必要とします。「いつもと違う」ことが不安
なので、「いつもと同じ」にこだわるわけです。
でも、「いつもと同じにこだわる」ことは長所でもあって、彼らは一回学習したルーテ
ィンの活動は、ものの見事に丁寧に再現できます。こだわるからこそ、学習が積み重
なっていきます。こだわりをうまく生かすと、パターン学習でいろいろなことを学べる
と思います。ただ、応用するのは苦手です。
苦手は責めずに支援する、強みを生かすという心構えで接すると、教える側も、教
わる側もラクになるのではないでしょうか。
心の育ちをサポートする
2019/01/04
子どもの「波長」に大人が合わせていく
大人の私たちからすると、子どもには意味不明な行動があるもので
す。その困り感が強いか、弱いかの違いだけで、実はどの子もさまざま
な特性や能力を持っています。そうした子どもの特性や能力について学
ぶことで、指導が豊かになり、質が上がるのではないかと思っています。
私自身、保育士時代、発達障害についてまだ深く学んでいないとき、
何をどうやっても、どうかかわっても、うまくいかない男の子がいました。
私が近づくと逃げてしまう。私とその子は大きく「波長」が違ったの
です。そこで、自分の「波長」に彼を合わせるのではなく、彼の「波
長」がどこにあるのか探ろうとしました。そのチューニングに半年ほど
かかった記憶があります。
その子はカナ—タイプの自閉症で、重度の知的障害を持っていました。
言葉も出なかったですし、昼寝もしません。給食もまったく食べませんで
した。ただ、よく、ジャングルジムに上り、空を見上げて、ずーっと手を
ひらひらと楽しそうに振っていました。そこで私も、彼と同じようにやっ
てみたんです。そうすると、なんとなく同じ瞬間に、キャッキャッと笑っ
たり、「あ、いたんだ」と気づいたりしてくれるようになりました。
子どもは、大人にありのままを受け容れられた、と感じたとき初めて
「発達したい」と思うものです。ですから、たとえ少しのずれであっても、
最初はその子の「波長」、言い換えれば「特性」に、大人の側が合わ
せるべきだと思います。彼との出会いは、私が発達障害について深く
学ぶきっかけとなりました。
続く・・・・