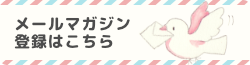- 藤原への講演依頼
- その他のお問い合わせ
| info@childhoodlabo.link childhoodlabo@gmail.com |
|
| 電話・FAX | 042-405-4181 |
| 住所 | 東京都府中市東芝町1-64-640 |
- 保育所等訪問支援に関するお問い合わせ
| 電話 | 070-2835-2708 藤原まで |
|---|
- ホーム
- ブログ
ブログ
E-leaning
2016/04/29安心して話せる大人
2016/04/26こどもは感性が豊かです。
発達障害のある子どもたちは、自分が生き抜くために
とても鋭い感性をもっているなあと
感じることがあります。
サバイバルスキルとでもいうのでしょうか、この人は信頼できる
信頼できないという感覚を、的確に判断しているという感じです。
こどもに安心感を与えられる人になりたいと
常に考えている私です。
どうしてかというと、その人に安心感を感じられないとこどもは自分の感じ方を
素直に表現してくれないからです。
私たちと違うものさし・・独自のものさしをもっている場合
そのものさしを、率直に教えてもらえないと適切な支援につながらないのです。
もちろん、日頃は大人が多分こうだろうと仮説を立てて、支援していくのですが
本人から教えてもらえたら、これほど楽で、正確な情報はありません。
ここで大切なのは、支援者が「多様性への寛容さ」、「柔軟なハート」をもつことなのです。
それを、自分の胆(きも)として据えているかどうかです。
ここを子どもたちは見抜くのだと思うのです。
この胆の据わった人になれれば、子どもは安心して、素直に話してくれると
私は信じています。
自分のものさしを横に置いて、子どものものさしを大切に大切に扱うことです。
そして、子どものものさしを尊重する感性を磨くことです。
<大切なあなたへのメッセージ>
私を信じて、自分のものさしについて話してくれた君。
私はあなたの力になりたいと思っています。
これからも、必要な時はどうぞ話に来て下さい。
いつでも待っています。
あなたの身近なサポーターより
園内研修
2016/04/23昨日は、保育園の園内研修に読んでいただきました。
実はこの研修は3回継続の研修で、ペアレントトレーニングの方法を学んで
保育に生かしてもらうものです。
1回目は、こどもの発達特性(脳の働き方)と支援の方法について話しました。
というのは、ペアレントトレーニングの方法・・は万能ではないからです。
お子さんの状況によっては、違う支援方法を使うほうがよいこともあるからです。
いずれにしても、まずは、こどもの現在の発達をしっかりとらえたうえで
その子の示す行動の理由を考えることが大切なのです。
それを理解したうえで、どの支援方法を使うのか?
1回目は、行動の理由を脳の働きから解説しました。
2回目は、いよいよペアレントトレーニングの演習です。
先生方に疑似保護者になってもらい、実際のペアレントトレーニングを体験してもらいます。
そして、ほめて、子どもとの良い関係を作る→その結果こどもの困った行動を軽減する
という学びです。
次回も、楽しく研修しますので
よろしくお願いいたします。
4月29日。30日は宮崎で研修です
2016/04/22私が副会長をしている「こども家族早期発達支援学会」
ゴールデンウイークの入り口の
4月29日と30日に公開講座を宮崎で開催します。
この講座を受けると「早期発達支援士」資格の認定講座に移行することもでき
専門的な資格を取りたいと考えている方も是非ご参加いただければと思います。
くわしくは「こども家族」と検索していただいて
学会のHPにいらしてください。
当日参加もありです。
| 日付 | 会場 | 時間 | 領域 | 講座名 | 担当講師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月29日 (金/祝) | 宮崎市民プラザ ギャラリー (宮崎市橘通西1-1-2) | ① | 家族 | E-011: 家族を支える福祉 | 田畑寿明 |
| ② | 心理・ アセスメント | E-005: 乳幼児期の発達の心理検査とインフォーマルアセスメント | 岩﨑まり子 | ||
| ③ | 医療・保健 | E-003: 発達障がい・愛着障がい | 田中 哲 | ||
| 4月30日 (土) | 宮崎市民プラザ ギャラリー (宮崎市橘通西1-1-2) | ① | 発達・言語 | E-001: 発達を支援するということ | 藤原里美 |
| ② | 療育支援 | E-007: 環境の支援・行動の支援 | 藤原里美 | ||
| ③ | コーディネート | E-009: 関係機関(医療・福祉・教育)をつなぐ就学支援 | 岩﨑まり子 |
これからの幼児教育
2016/04/19ベネッセという会社をご存知ですか?
こどもチャレンジ・しまじろうの会社ですね。
実は、ベネッセ教育総合研究所という部門で
これからの幼児教育という冊子を年に2回ほど発行しています。
素晴らしい先生の記事がテーマにそって掲載されていて
なかなか読みごたえがあります。
実は今年の夏号に、私の記事がのることになりました。
特別な支援が必要な子どもたちの特集で
榊原洋一先生と藤原のラインナップだそうです。
先日、多様な子どもたちの発達支援というテーマで
保育現場の実情や、私が保育現場にしているサポート
また発達障害の子どもたちとのかかわりなど
インタビューを受けました。
プロの方の編集により、多分「素晴らしい記事」になるでしょう(笑)
WEB上でだれでも閲覧できるようになっています。
保育現場にも無料で配布されているという
太っ腹なベネッセさん。
バックナンバーはこちらから読むことができます。
http://berd.benesse.jp/magazine/en/backnumber/
熊本に思いをはせる
2016/04/17日常にある当たり前の幸せが
どんなにとおといことなのか。
明日食べることに、眠ることに、そして生きることに不安がないだけで
ありがたいことを
私たちは、こんな悲しい出来事から学ぶのです。
マグネチュード7!!
想像を超える出来事に
自閉症スペクトラムのある子どもたちは
どう過ごしているのか?
胸が痛くなります。
感覚の過敏さのある子は
常に揺れている感覚におびえているのではないでしょうか?
ただ祈るしかないですが
私は明日からできることにただただ向き合い
そばにいる子どもたち、ご家族、そして自身の家族の
幸せのために、ベストを尽くしましょう。
金曜日に研修にご参加いただいた
清瀬市の保育士さん。
「最後の言葉が身に沁みました」とお声掛けいただいた
保育士さん。
皆さんとつながれたこと、うれしく思います。
今年度は清瀬市の保育士さんの研修に9回お邪魔します。
そして
明日からまた、ともに子供たちに向き合いましょう。
文化の違いといえども
2016/04/13昨日、カナダの先生とSkypeにてオンラインEnglsh
フレーズ・オブ・ザ・ディーは
How was the trip?(旅行はどうだった?)
このフレーズは本当によく使いますよね
How was your school today?
How was your child?
さて、このオンラインイングリッシュの楽しみは
お国事情について知ることができること。
昨日はドラッグの話に
カナダでは、痛み止めなどにマリファナをつかうことがあるそうです。
そのせいか、マリファナは高校生でも簡単に
購入することができる・・・・えーっ!!
Really? と思わず。
日本では考えられないこと。
国として秩序や治安を守るために
様々な規制があるのは、子どもを育てる上には、やはり安心です。
ドラッグを使わなくても、日常の中に
楽しい体験がたくさん!!
ウキウキわくわくできることを
見つけてあげられればと思います。
もちろん、安心できることリラックスできることも
そして、毎日健康で過ごせること。
日常の中で小さな幸せを見つけられること。
まずは大人がそんな生活をしていくことが大切ですよね。
今朝、二男が目覚めすっきり起きてきた。
これは、本当にHappyな出来事。
長男も、元気に「いってきます」と出かけて行きました。
Happy2つゲットですね。
理想の子ども
2016/04/12理想の子ども
あなたが「こうなってほしいなあ」と、子どもに願うことは何ですか?よく保育園や学校の目標に
みんな仲良く 明るい元気な子ども 思いやりのある子ども
がんばる子ども チャレンジする子ども ねばり強い子ども
などなどありますが、この理想って全ての子にあてはまるのでしょうか?
また、幸せの感じ方も多様です。
新しいことや難しいことにトライして「やった」という達成感を味わうことが幸せ
のんびり、穏やかな日々を過ごすことが幸せ
人と思いを共有したり、人の役に立つことが幸せ・・・・
あなたはどのタイプですか?そして、あなたのお子さんも同じように幸せを感じるタイプですか?
大人が描く理想の子どもや、幸せの価値観を子どもに一方的に当てはめてしまうのは危険です。自分の幸せが、わが子の幸せとは限りません。自分とは別人格の、大切なわが子を幸せの在りj方を考えてみましょう。理想や、幸せに正解はないのですから。
「みんななかよく」なんて、ぼくにはできないから、学校にはいけない・・。といった自閉症スペクトラムの男の子を思い出します。そのくらい、大人の価値観に応じられない自分に対して苦しむ子もいるということを、私たちは忘れないでいましょう。
今日も良い天気ですね。みんないってらっしゃい。楽しい学校生活を送れますように!!
訪問サポートは一日かけて
2016/04/10保育園などの訪問は、1日かけて対応させていただきます。
午前中は各クラスの保育を見せていただきます。お子さんの様子を観察したり
お子さんに実際関わらせてもらい、また時に、簡単な検査をしたり
保育園の現状とお子さんのアセスメントを中心に・・
その後、昼食を一緒に頂きながら、先生と簡単な打ち合わせをして
子ども達が午睡に入った際に、1時間から2時間程度の研修を
園の保育士さん、全員にします。
テーマは園からの依頼に応じてさまざまです。
園によっては全スタッフに研修を受講させたいと
1時間を2回に分けて行うこともあります。
時間勤務のパート職員さんに参加いただくことも多いですね。
皆が同じ研修を受けるというのはとても意義深いとおもいます。
その後、スタッフの皆さんが同じ言葉で語り合えるということになりますので、
理解が深まると同時に連携がとりやすくなりますね。
その後、各クラスの先生方と、午前中の観察やアセスメントをもとに
順に話し合います。
個別の対応はもちろん、クラス運営について、環境調整について
保育プログラムについてなど、相談は多岐にわたります、
できるだけ、クラスの先生のニーズに応じて
明日から実践できることをお伝えします。
お子さんに関しては、お子さんの状態について通訳して
理解をすすめるように努力します。
こうして一日はあっという間に過ぎてしまいます、
全クラス回るのは1日では難しいというのが正直なところですが、
とにかく分刻みで各クラスをまわり、限られた時間の中で
できるだけ適切なアドバイスを数多くお伝えできるように努力します。
チャイルドフッドラボは
一日かけての訪問を大切にしています。
その中での研修も大事に考えています。
現場に近いところで、支援をしたい
チャイルドフッドラボは願っています。
新年度とタイムマシーン
2016/04/07新年度を迎えるこの時期。
もしあなたがタイムマシーンを使えるとしたら
みらいに行きたいですか?過去に戻りたいですが?
私は人生を半分以上生きている年齢なのでもちろん過去に戻りたいですが
新学期を迎えた子どもたちには、未来にいってみたいと・・
みらいに心を馳せてほしいなあと思います。
でも、自閉症スペクトラムのある女の子は
6歳の時にこう言いました。
「赤ちゃんからやり直したい」と
1年生の男の子も、何か失敗をすると
「藤原先生、時間を戻して、もう一度やるから」と
タイムマシーンを使えたら、何度過去に戻りたいと願っていたか。
うまくいかない自分を抱えて、小さな心を痛めていました。
自閉症スペクトラムのある子たちは、些細な失敗でも
この世の終わりの湯に感じてしまう、思考のクセをもつことがあるのです。
この思考のクセをもつと、
いつでも不安と隣り合わせです。
だから
私は繰り返し伝え続けます。
失敗は大事な出来事
失敗しながら、みんな大きくなるんだよと。
子どもたちは「失敗は成功のもと」
「あしたがあるさ」など、ポジティブなフレーズを魔法のことばとして
おまじないのように唱えながら
失敗を乗り越えていける力をつけていきます。
新しい環境にいる子どもたち
「失敗はせいこうのもとだよ」
そして、そのそばにいる大人たち
子どもを叱るのではなくて、次がんばろうと温かく励ましてくださいね。
入学式と低気圧
2016/04/05今日、入学式を迎えるお子さんが多いと思います。
ご入学おめでとうございます。
東京名あいにくの天気、雨が降っています。
こんなな時は雨降って地かたまるというのですね。
発達障害のあるお子さんは、感覚の過敏さをもつ子が多いのですが
これは低気圧に関してもよく見られます。
低気圧が来ると頭が痛くなったり、なんとなく調子がよくなかったり。
いつもよりイライラが強くなる子もいます。
入学式という、緊張をする行事のときは雨降ってほしくないなあ
というのは、低気圧来てほしくないなあと言い換えてもよいかも。
リラックス、リラックス。
大丈夫だよ新入生。
あなたのことは、わかっているから。
と、彼らの「ものさし」に心を馳せながら。

チャイルドフッドラボは
発達障害のある子、支援が必要な子を支援する方たちを
応援、サポートしています。
来週からURLが変わります。
新URL
です。
今後ともよろしくお願いいたします。
URL変わります
2016/04/02現在のURLは
ですが、来週をめどに
に変わります。
もうお分かりと思いますが、childhoodのスペルをchildfood
と間違えて登録していました。
不注意この上ないです!!
合わせてお問い合わせメールのアドレスもかわります。
新しいアドレスは
となります。
よろしくお願いいたします。
自閉症スペクトラムとその子らしさ
2016/04/05
私たちは風邪をひくと、病院に行ったり、薬を飲んだりして風をやっつけて病気を治します。
つまり自分の風を分けて考えることができます。
でも、自閉症スペクトラムをもつ子は、その特性とそのこを分けて考えることはできません。
ところが私たちは時に、自閉症スペクトラムをまるで悪いことのように考えて攻撃してしまうことがあります。
自閉症スペクトラムの特性の変化をターゲットにし、時に攻撃すると、それはその子らしさを否定することになります。それは、こどもを傷つけ、不安にさせ、自尊心を下げてしまいます。
私たちはそこに気をつけて関わらなければいけません。
もちろん、特性から来る生活の困難さは改善させたいと思うし
そのために、環境を調整したり、発達を促す遊びを提供したり
私たちは支援や療育をします。
でも、常に心に留めておくことは、「自閉症スペクトラム」を含めてその子を丸ごと受け止めるということなのです。実はこれは、結構しんどいことです。言葉にするのは簡単ですが、なかなか難しい。
このときに常に心に留めておくことは、自閉症スペクトラムをもつ子どもが、そうでないたくさんの人と生きるのは大変な努力のいることだということ。
だから、周囲の私たちもこども達と同じように努力しなければならないと思います。
私はそう思って、支援を続けています。
私の身近にいる保育士さんたちも、まさにそれを実践しています。
こどもに寄り添ううため、理解するための努力、学びには頭が下がる思いです。
私もこの研究所を通じて、自閉症スペクトラムのこどもと共の生きている保育士さんたちの
お手伝いができればと思います。
そのこらしさを、否定せずに支援ができるように、努力をしていきたいと思います。
宇多田ヒカルさん新曲
2016/04/05いま、テレビから宇多田ヒカルさんの新曲がながれてきました。
歌詞を聞いて、これは発達障害や発達に偏りをもつお子さんの
お父さん、お母さん、
支援をしてる保育士さんや先生方の
思いとリンクするなあと感じました。
「誰かに手を伸ばし
あなたに思い馳せるとき
あなたに聞きたいことがいっぱい
あふれてあふれて、、」
お子さんの言動にとまどい、時に悩んでいるときに
誰かに助けを求めて
お子さんに思いを 馳せる
そして、あなたの世界についておしえてほしい・・。
そう願うことは多いと思います。
自分のものさしとちがうものさしをもっていお子さんを理解するときに
その子の見え方感じ方に近づきたい。
それがわかれば、適切な支援の方策に近づくのに・・と何度思ってことでしょう。
人を理解し、支援するときに、誰でも経験することですね。
でも、それぞれい違う人ですから
相手のすべてを理解するのは不可能なのです。
だからこそ、私たちは学び続けるのだと思います。
私もまだまだ、発達途上、これからも、真摯にこどもから
ご家族から、そして様々な本から研修から
学ぶ1年にしたいと思います。
弱点です
実は前庭感覚が敏感です
2016/04/04
皆さんは前庭感覚というのをご存知ですが?
自分の頭の位置がまっすぐなのがわかる、バランスをとるときに使う
スピードを感じたり、回転を感じたりする体の内側にある感覚です。
私はこの感覚がどちらかといえば敏感で、揺れる感覚に弱いのです。
新幹線や飛行機など乗り物に弱い。
こうなると長距離の移動は結構大変です。
ここ何年か、東京以外の場所からも、研修講師などで読んでいただけることが増え
それはとてもうれしいことですが
それなりに準備をしていきます。
まずは、乗り物酔いの薬を必ず飲み、もちろん携帯していきます。
座席は、進行方向一番前の通路側
洗面所に近いところですね。
そして、乗り物の中ではできるだけ寝るようにしています。
回数を重ねるにつれ、すこしずつ、強くなっているようには感じています。
前回の金沢往復では、短時間パソコンを操作することもできましから。
(北陸新幹線に初めて乗りました。車内快適でした。各座席にコンセント付き)
発達障害をもつ子はこの感覚に偏りがある場合も少なくありません。
敏感な子は、日常生活の中でちょっとしてことで頭がくらくらしているんじゃないかなあと思います。
私はその子たちの気持ちが少しわかるタイプですね。
今年は、研修で宮崎(4月最終週の土日です、詳しくはこども家族早期発達支援学会のHPで)
北海道(2回)、大阪、沖縄、広島に行く予定です。
工夫しながら、長距離の旅も楽しめるようになりたいと思います。
何か良いアイデアがある方は是非メールください(笑)。
こどもの気持ちがよくわかる (疑似体験)
2016/04/03今朝、9時から10時まで、オンラインの英会話。
この体験が、まさにコミュニケーションに困難をもった子どもたちの疑似体験なのです。
もう想像がつくと思いますが、簡単なことも言いたいのに言葉が浮かばないもどかしさ
やっと出てきたセンテンスも、Wordの並び方がちがったり(文法) aを忘れたり、複数形の s をつけなかったり
Perfect!!と先生に言ってもらえることが少なすぎる(笑)
でも、「大丈夫、つうじますよそれで」「ほとんどよかった、ここだけ直せばパーフェクトです」など
はげまし、そして前に進んでくれる先生方。
私は間違えてもめげずに教えてもらえるタイプなのでよいのですが、
間違えたらどうしようなどと思ってしまう思考のタイプをもっていたら。
伝えられなくなるのは、当然です。
言葉を使うのに、こんなに頭を使う・・ものすごいエネルギーですね。
無意識に気楽に言葉が出てくる生活のなかで
この経験は本当に貴重。
私の研修でも疑似体験は必ずと言っていいほど入れるのですが
「こどもの気持ちがよくわかった」「こんなに大変なんだ」ということがわかると
こどもへのかかわりや声かけが変化していきますね。みなさん。
相手の立場に立って、感じられる感性。
そのために、私は発達障害をもつ当事者の方の本を
定期的に読むようにしています。
自分の感性と違う人の感性に触れることで
自分の物差しの幅や種類が増えますから。
単一の幅の狭い物差ししか持てない場合。
多様な子どもたちの発達支援は、できませんから。
えいかいわ英会話は、こうした視点からもまだまだやめられませんね。
パンフレットできました!
2016/04/02チャイルドフットラボは
発達障害をもつおこさん、また発達の気になるお子さんの
保育、支援をサポートするために設立しました。
長らく療育や、地域の園のサポートをしてきたスタッフが
それぞれの現場のニーズに応じた
コンサルテーションを行います。
パンフレットが出来上がりました。
是非ご覧ください。
PDFファイルになっているので、印刷し、三つ折りにすると
見やすくなります。
2017年〜たくさんの現場にお伺いできたらと
今から楽しみにしています。