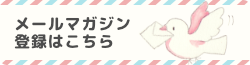- 藤原への講演依頼
- その他のお問い合わせ
| info@childhoodlabo.link childhoodlabo@gmail.com |
|
| 電話・FAX | 042-405-4181 |
| 住所 | 東京都府中市東芝町1-64-640 |
- 保育所等訪問支援に関するお問い合わせ
| 電話 | 070-2835-2708 藤原まで |
|---|
- ホーム
- ブログ
ブログ
心の育ちをサポートする
2019/01/04
子どもの「波長」に大人が合わせていく
大人の私たちからすると、子どもには意味不明な行動があるもので
す。その困り感が強いか、弱いかの違いだけで、実はどの子もさまざま
な特性や能力を持っています。そうした子どもの特性や能力について学
ぶことで、指導が豊かになり、質が上がるのではないかと思っています。
私自身、保育士時代、発達障害についてまだ深く学んでいないとき、
何をどうやっても、どうかかわっても、うまくいかない男の子がいました。
私が近づくと逃げてしまう。私とその子は大きく「波長」が違ったの
です。そこで、自分の「波長」に彼を合わせるのではなく、彼の「波
長」がどこにあるのか探ろうとしました。そのチューニングに半年ほど
かかった記憶があります。
その子はカナ—タイプの自閉症で、重度の知的障害を持っていました。
言葉も出なかったですし、昼寝もしません。給食もまったく食べませんで
した。ただ、よく、ジャングルジムに上り、空を見上げて、ずーっと手を
ひらひらと楽しそうに振っていました。そこで私も、彼と同じようにやっ
てみたんです。そうすると、なんとなく同じ瞬間に、キャッキャッと笑っ
たり、「あ、いたんだ」と気づいたりしてくれるようになりました。
子どもは、大人にありのままを受け容れられた、と感じたとき初めて
「発達したい」と思うものです。ですから、たとえ少しのずれであっても、
最初はその子の「波長」、言い換えれば「特性」に、大人の側が合わ
せるべきだと思います。彼との出会いは、私が発達障害について深く
学ぶきっかけとなりました。
続く・・・・
ラボの研修はコミュニティー
2018/12/09来年度のラボの研修が、次々に決まり始めています。
研修は学びの場
でもそれだけではありません。
子どもの幸せを願う人たちのコミュニティーでもあります。
それぞれの現場で、悩んだり、考え方の相違から孤独を感じたりすることもあるかもしれません。
そんな時にラボの研修に参加されると
「仲間がいる」「一人じゃないんだ」「共に頑張るんだ」
と感じ、「やっぱり、私は私のままでいいんだ」
「みんなちがってみんないい」・・・・そうなのです。
ラボの支援の方法は、まだまだ少数派なのかもしれません。
それでも、私は子どもたちの「その子らしさ」を生かして
「ふつう」を目指すことなく、幸せをつかんでほしい
そのために、支えたいのです。
これからもこの考えをぶれることなく皆さんと共有していきたいと思います。

支援者とご家族の協働ケーススタディ
2018/11/25昨日、小平市の障害福祉課、NPO法人子ども未来ラボさんとの協働事業
ペアレントプログラムが終了しました。
この事業は、ご家族の方約20名が藤原のペアトレ6セッションに隔週でご参加いただきます。
その様子を、小平市の保育士さんなどの支援者に見学してもらい
家族の支援について、学んでいただくスタイルをとっています。
日本で初めての試みだと自負していますが
最後は、支援者と、ご家族が一つのグループになり
ケーススタディー(インシデントプロセス法)を行いました。
その光景が、もう温かくて涙が出そうなくらい。
支援者も家族もそれぞれの立場、関係なく、お子さんの支援について語り合い
アイデアを出し合います。
皆さん笑顔で「楽しかったー」と・・。
みんなで支えあう、一人じゃない・・こんなに見方がいるということを
実感した最後のセッション。
皆さんの、この思いは明日につながります。そして、子どもたちにつながります。
私も素敵なエネルギー、いただきました。
本当にありがとうございました。
最後にサプライズでキャンドルいただきました。
この研修で灯った温かい支援を火をつないでいきたいと思います。
保育士さん、応援してます。
2018/10/17昨日、今日は保育士さんオンリーの研修
実は私も保育士で、保育現場を巡回することも多い。
保育園での支援が大変なことは重々知りながら
保育園でできることは沢山あること
そして、日々積み重ねることで子どもの発達支援にものすごい影響があることを
丁寧にお伝えしています。
皆さんが、やってみよう。というモチベーションが上がるように祈りつつ。
思考のクセと「ほいくあっぷ」
2018/10/14明日、取材があります。早いものですでに12園以上の訪問をしてきました。
来年も継続して、この連載は続きます。
ここでもいつも大切にしていることは
「強みを生かす」
「うまくいかないときは子どものせいにもしない、先生のせいにもしない、アイデアが足りないと考える」
今月のテーマは「限られた環境の中で工夫する」
今ある環境をどう生かすか?工夫するか?
たとえば、コップの中に水が半分は言っていたら
「半分しか入っていない」というかんがえもあれば
「半分も入っている」というかんがえもある。
常に後者・・・そんな思考のクセをつけたいものです。