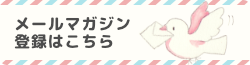- 藤原への講演依頼
- その他のお問い合わせ
| info@childhoodlabo.link childhoodlabo@gmail.com |
|
| 電話・FAX | 042-405-4181 |
| 住所 | 東京都府中市東芝町1-64-640 |
- 保育所等訪問支援に関するお問い合わせ
| 電話 | 070-2835-2708 藤原まで |
|---|
心の育ちをサポートする4
2019/01/11子どもの心に寄り添いながら共感→受容→提案する
発達障害がある子どもたちと接するとき、その子たちの心の状
態に寄り添って支援する、という姿勢がとても大切です。
私が研修に行った園で出会った、ASD(自閉症スペク
トラム障害)の男の子の例を紹介します。
ASDの子は急な変更が苦手です。その日は、外遊びのとき、
最後にゲームをするはずだったのに、時間が足りず急にや
らないことになりました。その子は大変なパニックにな
り、泣いて怒っていました。
担任の先生は、「君の気持ちはわかるけど、あきらめよう
よ」と説得していましたが、彼の気持ちはおさまりません。
そこで私は、彼に次のように話しかけました。「急にゲームがな
くなったんだって? それは泣いちゃうよね、怒っちゃうよね。
君の気持ちはよくわかる。怒るのは当然だと思うよ」。すると、そ
の子の声のトーンがすとんと落ちました。さらに私は続けました。
「問題なのは急に変わったってことだよね? 君はゲームがなくな
ることを知らなかったんだよね?」と言ったら、彼は「そうそう」
とうなずきました。「だったら、急に変えるのはやめてって先生に
お願いしたら?」と言ったら、もう泣くのをやめました。そして、
先生のところに行って「先生、最初にゲームがあるかないか教えて」
と自分の言葉で言ったのです。先生は「わかった、そうするね」
と答えました。彼はほっとした顔になって、給食を食べに行きま
した。
「そんなことぐらい?」と思われるかもしれませんが、彼にとっ
てゲームがなくなるというのは「そんなことぐらい」で済むこと
ではなかったのです。泣いて怒るほどつらいことだったのです。
それを、大好きな先生に「そんなことぐらい」と思われたら、彼
の心はさらに傷つきます。そして、その後も彼のつらさを無視し
た対応がくり返されたら、彼は「またか、また叱られるんだ、ま
た僕が悪いのか」と、どんどん自己肯定感を低めていくことにな
りかねません。
共感して、受容して、提案する。子どもの心を育てるには、ま
ずは「共感」が大切だと思います。
「こうしなさい」と押しつけるのではなく、しっかり共感して心
が開いてから、「これ、どう?」と提案する。そうすると、子ども
たちは素直に聞いてくれると思います。
次回に続く・・・