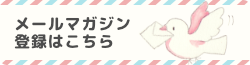- 藤原への講演依頼
- その他のお問い合わせ
| info@childhoodlabo.link childhoodlabo@gmail.com |
|
| 電話・FAX | 042-405-4181 |
| 住所 | 東京都府中市東芝町1-64-640 |
- 保育所等訪問支援に関するお問い合わせ
| 電話 | 070-2835-2708 藤原まで |
|---|
- ホーム
- ブログ
ブログ
できないことを責めない
2018/04/154月、それぞれの現場でのスタッフの移動など
変化が大きい今月。
特に新人で現場デビューした人は不安でいっぱいの日々でしょうね。
この時期時に心掛けたいのは
「できないことを責めない」ということでしょうか?
できないことをできるようにさせるために指導したり教育したりするのが常ですが
不安の大きい場合、このできないことにフォーカスをあてられるのはとてもしんどいのです。
できることにこそフォーカスをあてて、そこを伸ばすことに自分をフォーカスさせる。
できていることを認めることで、できない部分が伸びていく。
これは発達支援によくあることです。
指導や教育は、できないことを責められるように感じることもあります。
指導や教育は、できることを伸ばすことに活用したいですね。
できないことに関しては、こうしたらうまくいくという方法をモデルを示しながら
自分でやって見せるといいですよね。
自然に見て学ぶことができれば、できない自分を責めずにすみます。
いつかは、あんな風な支援者になりたいと、思ってもらえるような人材になりたいなあと
毎年4月を迎えるたびに思います。

撮影終わりました
2018/04/07昨日の、医学映像教育センターのビデオ番組の収録ですが
10分程度の解説に、準備から、撮影まで3時間半かかりました。
丁寧に、撮影、そのあと環境の撮影(専門用語ではブツドリというそうです)
ライト2台とカメラ3歳、そのほか多くの機材
さすがプロという感じです。
いままで、E−leaning用の撮影を2回経験していますが
カメラの前でしゃべるのは・・私らしくない感じ
昨日も立ち位置を指定され
動かすにはなす。
子の動かずに人を固くするね^^
自然にふるまえない感じ。
やはり私の研修はライブがいいです(笑)
でも多くの方に、学んでいただくためにこの映像での配信は必須ですから
いつもと違う藤原を味わっていただく(笑)良い機会かも。
動かないで!!でその人らしさを
封印されることを改めて感じた1日でした。
でもでも、映像は絶対素敵な出来栄えですよ。
なにせ、プロが編集するのですから。

撮影
2018/04/07今日は、医学映像教育センターのビデオ番組の収録にいってきます。
私がスーパーバイズさせていただいている発達支援事業所
キートスさんでの撮影です。
10分ほどの出演になるのですが、発達障害のある子どものかかわり方のポイントについて
お話ししてきます。
田中哲先生の監修での出演です。
楽しみです。

発達支援事業所
2018/03/21来年度から継続しての事業所を含め
4つの発達支援事業所のスーパーバイザーとして
スタッフの育成や、療育プログラムの質の向上、およびお子さんやご家族のコンサルテーションなど
お手伝いをさせていただきます。
発達支援事業所とは
児童福祉法に基づくサービスの一つです。
早期から発達が気になるお子さんを対象に、障害の有無に関わらず 利用できる療育施設です。
国と自治体の給付により、ご利用料のうち1割のご負担で利用が可能というシステムになっています。
(利用のシステムについては各事業所に問い合わせると丁寧に説明してもらえます)
先日は、和光市に4月からOPENする
Rootsのスタッフ研修を実施しました。
地域の子育て中のご家族の含め20名程度の方にご参加いただきました。
最後に皆さんに感想を言っていただいたのですが
「この研修で自身の理解が深まった」という内容が
いくつも出されました。
そうなんですね。発達を学ぶと自己理解が深まります。
子どもと関わるためには、この自分を知る作業が不可欠。
そして、その自分を大切に受け入れる作業が。
ここに気づくと、子どもへの多様性への寛容さが
そして愛情が、親和性が強まるのです。
少人数での研修は、参加した方の思いが
強く共有され、思った以上の変化が生じることを
感じられた研修でした。
今週の金曜日もさらに6時間学びあいをしてきます。
素敵な発達支援が提供される事業所になるでしょうね。
Rootsのホームページは
発達サポーター認証講座
2018/03/20今年度の発達サポーター認証講座
基礎編・応用編(夜間)・コーディネーター編が
今週ですべて終了します。
全10回の講座。
土曜日お休みの日に
お仕事帰りの夜に
そして木曜日の午後仕事のお休みを取ってと
ご参加の皆様がご参加くださいました。
総数130名
毎回皆様とお会いできること
そして、素敵なリアクションとワークショップ
研修はライブ感が大切で
来ている方同士のつながりによる化学反応が
ものすごいエネルギーになっていると感じていました。
知識や技術を得るだけでなく
新しい自分を発見したり、元気を取り戻したり
人に癒されたり、励まされたり。
人とのつながりの中で学びが深くなる・・。
来年度の研修も、さらにブラッシュアップしたものにしていきます。