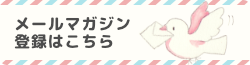- 藤原への講演依頼
- その他のお問い合わせ
| info@childhoodlabo.link childhoodlabo@gmail.com |
|
| 電話・FAX | 042-405-4181 |
| 住所 | 東京都府中市東芝町1-64-640 |
- 保育所等訪問支援に関するお問い合わせ
| 電話 | 070-2835-2708 藤原まで |
|---|
- ホーム
- ブログ
ブログ
自閉症スペクトラムとその子らしさ
2016/04/05
私たちは風邪をひくと、病院に行ったり、薬を飲んだりして風をやっつけて病気を治します。
つまり自分の風を分けて考えることができます。
でも、自閉症スペクトラムをもつ子は、その特性とそのこを分けて考えることはできません。
ところが私たちは時に、自閉症スペクトラムをまるで悪いことのように考えて攻撃してしまうことがあります。
自閉症スペクトラムの特性の変化をターゲットにし、時に攻撃すると、それはその子らしさを否定することになります。それは、こどもを傷つけ、不安にさせ、自尊心を下げてしまいます。
私たちはそこに気をつけて関わらなければいけません。
もちろん、特性から来る生活の困難さは改善させたいと思うし
そのために、環境を調整したり、発達を促す遊びを提供したり
私たちは支援や療育をします。
でも、常に心に留めておくことは、「自閉症スペクトラム」を含めてその子を丸ごと受け止めるということなのです。実はこれは、結構しんどいことです。言葉にするのは簡単ですが、なかなか難しい。
このときに常に心に留めておくことは、自閉症スペクトラムをもつ子どもが、そうでないたくさんの人と生きるのは大変な努力のいることだということ。
だから、周囲の私たちもこども達と同じように努力しなければならないと思います。
私はそう思って、支援を続けています。
私の身近にいる保育士さんたちも、まさにそれを実践しています。
こどもに寄り添ううため、理解するための努力、学びには頭が下がる思いです。
私もこの研究所を通じて、自閉症スペクトラムのこどもと共の生きている保育士さんたちの
お手伝いができればと思います。
そのこらしさを、否定せずに支援ができるように、努力をしていきたいと思います。
宇多田ヒカルさん新曲
2016/04/05いま、テレビから宇多田ヒカルさんの新曲がながれてきました。
歌詞を聞いて、これは発達障害や発達に偏りをもつお子さんの
お父さん、お母さん、
支援をしてる保育士さんや先生方の
思いとリンクするなあと感じました。
「誰かに手を伸ばし
あなたに思い馳せるとき
あなたに聞きたいことがいっぱい
あふれてあふれて、、」
お子さんの言動にとまどい、時に悩んでいるときに
誰かに助けを求めて
お子さんに思いを 馳せる
そして、あなたの世界についておしえてほしい・・。
そう願うことは多いと思います。
自分のものさしとちがうものさしをもっていお子さんを理解するときに
その子の見え方感じ方に近づきたい。
それがわかれば、適切な支援の方策に近づくのに・・と何度思ってことでしょう。
人を理解し、支援するときに、誰でも経験することですね。
でも、それぞれい違う人ですから
相手のすべてを理解するのは不可能なのです。
だからこそ、私たちは学び続けるのだと思います。
私もまだまだ、発達途上、これからも、真摯にこどもから
ご家族から、そして様々な本から研修から
学ぶ1年にしたいと思います。
弱点です
実は前庭感覚が敏感です
2016/04/04
皆さんは前庭感覚というのをご存知ですが?
自分の頭の位置がまっすぐなのがわかる、バランスをとるときに使う
スピードを感じたり、回転を感じたりする体の内側にある感覚です。
私はこの感覚がどちらかといえば敏感で、揺れる感覚に弱いのです。
新幹線や飛行機など乗り物に弱い。
こうなると長距離の移動は結構大変です。
ここ何年か、東京以外の場所からも、研修講師などで読んでいただけることが増え
それはとてもうれしいことですが
それなりに準備をしていきます。
まずは、乗り物酔いの薬を必ず飲み、もちろん携帯していきます。
座席は、進行方向一番前の通路側
洗面所に近いところですね。
そして、乗り物の中ではできるだけ寝るようにしています。
回数を重ねるにつれ、すこしずつ、強くなっているようには感じています。
前回の金沢往復では、短時間パソコンを操作することもできましから。
(北陸新幹線に初めて乗りました。車内快適でした。各座席にコンセント付き)
発達障害をもつ子はこの感覚に偏りがある場合も少なくありません。
敏感な子は、日常生活の中でちょっとしてことで頭がくらくらしているんじゃないかなあと思います。
私はその子たちの気持ちが少しわかるタイプですね。
今年は、研修で宮崎(4月最終週の土日です、詳しくはこども家族早期発達支援学会のHPで)
北海道(2回)、大阪、沖縄、広島に行く予定です。
工夫しながら、長距離の旅も楽しめるようになりたいと思います。
何か良いアイデアがある方は是非メールください(笑)。
こどもの気持ちがよくわかる (疑似体験)
2016/04/03今朝、9時から10時まで、オンラインの英会話。
この体験が、まさにコミュニケーションに困難をもった子どもたちの疑似体験なのです。
もう想像がつくと思いますが、簡単なことも言いたいのに言葉が浮かばないもどかしさ
やっと出てきたセンテンスも、Wordの並び方がちがったり(文法) aを忘れたり、複数形の s をつけなかったり
Perfect!!と先生に言ってもらえることが少なすぎる(笑)
でも、「大丈夫、つうじますよそれで」「ほとんどよかった、ここだけ直せばパーフェクトです」など
はげまし、そして前に進んでくれる先生方。
私は間違えてもめげずに教えてもらえるタイプなのでよいのですが、
間違えたらどうしようなどと思ってしまう思考のタイプをもっていたら。
伝えられなくなるのは、当然です。
言葉を使うのに、こんなに頭を使う・・ものすごいエネルギーですね。
無意識に気楽に言葉が出てくる生活のなかで
この経験は本当に貴重。
私の研修でも疑似体験は必ずと言っていいほど入れるのですが
「こどもの気持ちがよくわかった」「こんなに大変なんだ」ということがわかると
こどもへのかかわりや声かけが変化していきますね。みなさん。
相手の立場に立って、感じられる感性。
そのために、私は発達障害をもつ当事者の方の本を
定期的に読むようにしています。
自分の感性と違う人の感性に触れることで
自分の物差しの幅や種類が増えますから。
単一の幅の狭い物差ししか持てない場合。
多様な子どもたちの発達支援は、できませんから。
えいかいわ英会話は、こうした視点からもまだまだやめられませんね。